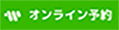2025/07/01
最近、愛犬が「たくさん水を飲んでいる」「毛が薄くなってきた」「なんとなくお腹がぽっこりしてきた」そんな変化に、不安を感じたことはありませんか?年齢を重ねた犬では、ちょっとした体の変化が見られることがありますが、これらの症状の裏に「クッシング症候群」という病気が隠れていることがあります。
クッシング症候群は、特に7歳以上の中高齢の犬によく見られるホルモンの病気です。初期症状が老化と見分けづらく、気づかれにくいこともあるため、飼い主様の早期の気づきが重要です。
今回は犬のクッシング症候群について、見落とされがちなサインや原因、診断方法、治療の流れ、そしてご家庭でできるケアなどを解説します。

■目次
1.クッシング症候群ってどんな病気?
2.主な症状と飼い主様が気づきやすいサイン
3.クッシング症候群の原因(3つのタイプ)
4.診断方法
5.治療方法とご家庭でのケア
6.まとめ
クッシング症候群ってどんな病気?
クッシング症候群は、「副腎皮質ホルモン(コルチゾール)」というホルモンが過剰に分泌されることで起こる内分泌疾患です。副腎とは、腎臓の近くにある小さな臓器で、代謝や免疫、ストレスへの反応など体のさまざまな働きに関わる大切なホルモンですが、過剰になると健康に悪影響を及ぼします。
この病気は、特に7歳以上の中高齢の犬に多く発症します。症状が多岐にわたるため、老化現象と間違えられやすく、早期に発見されにくいのが特徴です。放置すると症状が進行し、犬の生活の質が大きく低下してしまいます。そのため、できるだけ早く診断と治療を行うことが大切です。
主な症状と飼い主様が気づきやすいサイン
犬がクッシング症候群を引き起こすと、以下のような変化が見られます。
・多飲多尿
・脱毛や皮膚が薄くなる
・お腹がふくらむ(腹部膨満)
・元気がなくなる、運動を嫌がる
・息が荒くなる
最もよく見られるのが「多飲多尿」です。飲水量が以前と比べて増えている場合は、毎日決まった時間に水の減り具合を確認してみるのも一つの方法です。
また、「目の傷がなかなか治らない」「靭帯が傷みやすくなった」など、皮膚や関節の回復力の低下もクッシング症候群に関連しています。これは、コルチゾールが、皮膚や関節の健康を保つために必要な「コラーゲン」の合成を妨げてしまうことで起こります。
これらの症状は他の病気でも見られるため、自己判断せず早めに動物病院を受診しましょう。
犬や猫の関節痛の症状や治療法についてより詳しく知りたい方はこちら
クッシング症候群の原因(3つのタイプ)
クッシング症候群には、以下のように原因によって大きく3つのタイプがあります。
<下垂体性クッシング症候群>
最も多く見られるタイプで、全体の約85%を占めます。これは、脳の下垂体という部位に小さな腫瘍ができるタイプ、その腫瘍が副腎を刺激するホルモン(ACTH)を過剰に分泌することで、副腎からコルチゾールが多く作られてしまいます。
<副腎性クッシング症候群>
副腎そのものに腫瘍ができるタイプで、全体の約10〜15%を占めます。この腫瘍が直接コルチゾールを過剰に分泌することで症状が現れます。腫瘍が良性か悪性かによって治療方針が変わるため、慎重な検査と判断が必要です。
<医原性クッシング症候群>
ステロイド薬を長期間使用したことによって起こるタイプです。ステロイドは炎症や免疫反応を抑えるために用いられますが、過剰または長期の使用によって副腎の機能が抑えられ、ホルモンバランスが崩れてしまうことがあります。この場合、薬の減量や中止を含む治療方針の見直しが求められます。
診断方法
クッシング症候群の診断には、いくつかの段階を踏んだ精密な検査が必要です。一般的な血液検査だけでは確定診断が難しいことが多く、以下のような検査が行われます。
<ACTH刺激試験>
コルチゾールの分泌を促すACTHを投与し、反応を確認することで副腎機能を評価します。
<低用量デキサメタゾン抑制試験>
デキサメタゾンという薬を用いてホルモンの抑制反応を確認し、クッシング症候群の有無を判断します。
<超音波検査・CT検査>
副腎の下垂体の腫瘍の有無・位置・大きさを詳しく評価する精密な画像検査です。
また、診断が確定するまでは複数回の通院や検査が必要になる場合もあります。正確な診断が最適な治療に繋がるため、獣医師の指示に従って根気よく検査を進めることが大切です。
治療方法とご家庭でのケア
クッシング症候群の治療は、原因や犬の状態によって異なりますが、一般的には以下のような方法があります。
<内科治療(投薬)>
最も多く行われるのが、コルチゾールの過剰な分泌を抑える薬による治療です。投薬は継続的に行う必要があり、定期的な血液検査によって薬の効果や副作用を確認しながら、用量を調整していきます。生涯にわたる管理が必要なことも多いため、飼い主様の協力が重要になります。
<外科治療(手術)>
副腎に腫瘍がある場合、外科的に腫瘍を摘出することも選択肢のひとつです。ただし、手術のリスクや犬の年齢、全身状態によっては実施できないケースもあるため、慎重に検討する必要があります。
<ご家庭でできるケア>
治療と並行して、ご家庭では以下を行うことが大切です。
・飲水量や尿量の記録をつける
・食欲や体重の変化に注意を払う
・ストレスの少ない生活環境を整える
また、治療中に嘔吐や下痢、食欲不振などの副作用が現れた場合は、早めに動物病院を受診しましょう。こうした小さな変化にも注意を払うことが、犬の健康維持にとって非常に大切です。
まとめ
クッシング症候群は、犬に多く見られる慢性のホルモン疾患です。早期に気づき、適切な検査と治療を行うことで、症状をうまくコントロールしながら、快適な生活を維持することができます。
「少しでも様子がおかしいな」と思った時点で動物病院を受診することが、病気の早期発見につながります。特に多飲多尿や脱毛、活力の低下といった何気ない変化を見逃さないことが、愛犬の未来を守る第一歩になります。
当院では、ホルモン疾患に関する検査や治療にも対応しております。気になる症状がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
⬇️🌟この情報が役に立った方は、星をタップして応援してください🌟⬇️
■関連する記事はこちらから
埼玉県川口市・さいたま市(浦和区)・越谷市を中心に診療を行う
森田動物医療センター
当院の診療案内はこちら
※お電話でもご予約・ご相談を承っております