2025/05/16
最近、愛犬が普段よりもたくさん水を飲むようになったり、尿の量が増えたりしていませんか?
こうした日常のちょっとした変化は、シニア期の犬に多く見られる「慢性腎臓病」が関係している可能性があります。腎臓は血液をろ過し、老廃物を尿として体外に排出する重要な臓器です。しかし年齢とともに少しずつ機能が低下していき、気づいたときにはすでに症状が進んでいることもあります。
慢性腎臓病は一度発症すると完治が難しい病気ですが、早期に発見し適切な治療やケアを行えば、進行をゆるやかにできます。その結果、愛犬とより長く穏やかな時間を過ごすことが可能です。
今回はシニア犬の慢性腎臓病について、症状や原因、治療法からご家庭でのケアのポイントなどを解説します。

■目次
1.シニア犬の慢性腎臓病の症状
2.慢性腎臓病の種類と進行ステージ
3.シニア犬の慢性腎臓病の主な原因
4.診断方法
5.治療方法
6.ご家庭でできるケアと管理法
7.シニア犬の腎臓病と長く付き合うためのポイント
8.まとめ
シニア犬の慢性腎臓病の症状
犬の腎臓病にはさまざまな種類がありますが、中でもシニア犬に多く見られるのが「慢性腎臓病(CKD)」です。この病気は「急性腎障害」とは異なり、数か月から数年にかけてゆっくりと腎機能が低下していくのが特徴です。
初期には目立った症状が現れにくいこともありますが、以下のような変化が見られる場合は、慢性腎臓病を引き起こしている可能性があります。症状に気づいたら、早めに動物病院を受診しましょう。
<すぐに受診すべき症状>
・嘔吐や下痢が続いている
・明らかに元気がなく、ぐったりしている
・食欲が全くない
・よだれを流すようになった
<数日以内に受診が望ましい症状>
・水を飲む量が急に増えた
・尿の量が明らかに増えた、または減った
・体重が減ってきている
・皮膚や口の中が乾いている
なお、「様子を見ても大丈夫かな?」と迷った場合も、自己判断は避け、獣医師に相談することが大切です。
また、定期的な健康診断が慢性腎臓病の早期発見にとって重要な鍵となります。特に、以下のような変化が見られた場合は、腎臓機能に異常が生じている可能性があります。
<健康診断で確認すべき変化>
・血液検査で腎臓の数値に異常が見られる
・尿検査で尿比重が低下している
・尿中にタンパクが検出される
健康な今だからこそ受けたい!犬や猫の定期健診で見える未来とは?詳しくはこちらから
慢性腎臓病の種類と進行ステージ
慢性腎臓病の進行度は、国際獣医腎臓学会(IRIS)によりステージ1から4に分類されます。数字が大きいほど重度になります。ステージ分類は、血液検査の数値で行われ、さらに血圧や蛋白尿によりサブステージと細かく分類します。治療方針や目標は、ステージにより異なります。
ステージが進行するほど治療も複雑になり、生活の質(QOL)に与える影響も大きくなります。そのため、できるだけ早期に異常に気づき、治療を始めることが重要です。
シニア犬の慢性腎臓病の主な原因
慢性腎臓病の原因はさまざまですが、最も多いのは加齢による腎機能の低下です。年齢とともに腎臓の細胞が傷つき、ろ過機能が低下していきます。
また、以下のような原因も慢性腎臓病の発症に関与することがあります。
・糸球体疾患などの先天性・後天性の腎疾患
・犬種による遺伝的要因
・腎毒性のある薬剤や食べ物の誤飲(例:ぶどう、レーズン、一部の鎮痛薬など)
・レプトスピラ感染症など、腎臓にダメージを与える感染症
・循環器疾患(心腎関連)や膵炎など他の疾患からの併発
・歯肉炎
このように慢性腎臓病にはさまざまな原因が考えられますが、なかにははっきりしないケースもあります。そのため、飼い主様が日常的に愛犬の様子を見てあげたり、動物病院で定期的な健康チェックを受けることが大切です。
誤食は命に関わることも…犬や猫にNGな食べ物や対処法などはこちらから
診断方法
慢性腎臓病の診断には、以下のような検査を実施します。これらを総合的に判断し、正確な診断と治療方針を立てていきます。
・血液検査:クレアチニンやSDMAといった腎機能を評価する数値を確認します。
・尿検査:尿比重や尿中のタンパク、潜血の有無などを調べます。
・画像検査:超音波検査(エコー)やX線検査で、腎臓の大きさや構造を評価します。
犬や猫の血液検査、尿検査、糞便検査についてより詳しく知りたい方はこちら
犬や猫の健康診断(心電図、血圧、レントゲン、エコー検査)についてより詳しく知りたい方はこちら
当院では、最新の検査機器を用いて早期診断・正確なステージ分類を行い、それぞれの状態に合った治療計画を立てています。
治療方法
犬の慢性腎臓病の治療方法は、基本的に以下のような対症療法を実施します。治療を行ううえで大切なのは、腎臓の働きをできるだけ保ちつつ、今出ている症状を緩和してあげることです。
<食事療法>
初期段階では専用の腎臓病食などの療法食への切り替えが中心となります。タンパク質やリン、ナトリウムを制限したバランスの取れた食事が、腎臓への負担を軽減します。
<輸液療法>
症状が進行して脱水が見られる場合には、皮下補液や点滴を行います。軽度であれば自宅での皮下補液も可能で、獣医師の指導のもと行います。
<薬物療法>
症状や合併症に応じて、吐き気止めや胃薬、血圧をコントロールする薬などを使用します。
症状が重度になると、入院による集中治療が必要になることもあります。もし何か疑問がございましたら、診察時に遠慮なくご相談ください。
ご家庭でできるケアと管理法
慢性腎臓病は動物病院での治療とあわせて、以下のようなご家庭でのケアも非常に大切です。飼い主様のちょっとした配慮が、愛犬の負担を軽減し、病気と付き合っていくうえで大きな助けとなります。
<水分摂取の管理>
腎臓の健康を保つうえで、大切なのは水分補給です。いつでも新鮮なお水が飲めるようにしておくことに加え、1日の飲水量を記録しておくと、異常の早期発見につながります。
たとえば急に水をたくさん飲むようになったり、逆に飲まなくなったりした場合は、腎臓の状態が変化している可能性があるため、早めに獣医師に相談しましょう。
<食事管理>
療法食は腎臓に配慮された特別なフードですが、なかには味に慣れず食べてくれない犬もいます。そのため、無理に与え続けるのではなく、嗜好性の高い療法食を獣医師と相談しながら選ぶことが大切です。
<体重・排尿のモニタリング>
慢性腎臓病では、体重や排尿の変化が体調を知る大切なサインになります。週に1回は体重を測り、その増減を記録しておくことを習慣にしましょう。また、尿の回数や量、色やにおいの変化もこまめにチェックすることが大切です。
<皮下補液の習得>
慢性腎臓病が進行してくると、体内の水分や電解質のバランスを保つために、皮下補液が必要になることがあります。動物病院での補液はもちろん大切ですが、獣医師の指導のもとでご自宅でも補液が行えるようになると、通院の負担が減り、愛犬にとっても安心できる環境でケアが続けられます。
不安な場合は無理をせず、動物病院でやり方を丁寧にご説明しますので、獣医師と一緒に少しずつ慣れていきましょう。
シニア犬の腎臓病と長く付き合うためのポイント
慢性腎臓病と診断された場合、生活の質(QOL)を維持しながら病気と向き合っていくことが大切です。そのためには、飼い主様が病気への理解を深め、ご家庭でできる範囲のサポートを無理なく続けていくことが求められます。
また、慢性腎臓病は単独で進行するとは限らず、心臓病や関節炎、認知症など、シニア犬に多いほかの病気と併発するケースも少なくありません。これらを見逃さないためにも、定期的な血液検査や尿検査に加えて、全身の健康状態を総合的にチェックすることが重要です。
まとめ
慢性腎臓病はシニア犬に多く見られる病気ですが、早期に発見して適切な治療やご家庭でのケアを行えば、穏やかで充実した生活を長く送ることが可能です。
また、飲水量や体重、食欲といった日常の小さなサインを見逃さず、定期的に健康診断を受けることが大切です。若い犬であれば年に1回、シニア犬の場合は年に2回の健診をおすすめします。
当院では、慢性腎臓病の診断から治療、在宅ケアまで総合的にサポートしております。不安な点や気になる症状がございましたら、いつでもご相談ください。定期健診のご予約も随時受け付けております。愛犬との幸せな時間が1日でも長く続くよう、私たちが全力でサポートいたします。
⬇️🌟この情報が役に立った方は、星をタップして応援してください🌟⬇️
■関連する記事はこちらから
進行が速い!犬の急性腎不全の症状や治療方法についてより詳しく知りたい方はこちら
埼玉県川口市・さいたま市(浦和区)・越谷市を中心に診療を行う
森田動物医療センター
当院の診療案内はこちら
※お電話でもご予約・ご相談を承っております

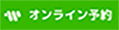

 (11 投票, 平均: 4.45 / 5)
(11 投票, 平均: 4.45 / 5)