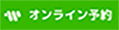2025/05/13
「最近、うちの犬が足先ばかり舐めている」「なんだか歩き方がぎこちなくて痛そう」と感じたことはありませんか?そのような行動には、実は皮膚トラブルが隠れている可能性があります。特に、犬が足の指と指の間を気にしているようであれば、「指間炎」を引き起こしているかもしれません。
指間炎とは、指の間の皮膚が赤く炎症を起こす病気で、かゆみや痛みを伴います。進行すると膿がたまったり出血したりすることもあるため、犬にとって大きなストレスになります。
この病気は、一度かかると再発しやすく、完治までに時間がかかることもあります。そのため、早期に気づき、原因を見極めて適切に治療を進めることが大切です。
今回は犬の指間炎について、症状のチェックポイントから原因、治療法、予防法などを解説します。

■目次
1.犬の指間炎チェックリスト
2.指間炎の主な原因
3.犬種別・環境別の注意点
4.診断方法
5.治療方法
6.ご家庭でできる指間炎のケアと予防法
7.まとめ
犬の指間炎チェックリスト
指間炎は、犬の見た目や行動から比較的早く気づくことができます。以下のような症状が見られる場合には、早めに動物病院で診察を受けるようにしましょう。
<すぐに受診すべき症状>
・指の間の皮膚が赤く腫れている
・膿が出ている
・出血している
・足を地面につけるのを嫌がる、または歩き方に違和感がある
・足先をしきりに舐めたり、噛んだりしている
<様子を見ながら受診を検討すべき症状>
・足の指の間に軽いかゆみや違和感があるように見える
・足先の毛が常に湿っており、乾きにくい状態が続いている
・足を舐める行動が以前よりも増えている
症状が軽度であれば、比較的短期間での回復も見込めますが、放置すると悪化してしまうことがあります。そのため、少しでも判断に迷ったときは早めに獣医師に相談しましょう。
指間炎の主な原因
指間炎を引き起こす原因は多岐にわたり、それぞれに応じた治療や対策が必要となります。
<アレルギー>
食べ物や環境中のアレルゲン(ハウスダスト、花粉、カビなど)が引き金となって、皮膚に炎症が起こることがあります。その結果、全身にかゆみが広がり、症状が慢性的に繰り返される傾向があります。
<細菌・真菌感染>
犬が患部を舐め続けると、その部分が湿った状態になり、細菌やカビ(真菌)が繁殖しやすくなります。悪化すると皮膚が化膿したり、強いにおいが出てきたりします。
<外傷・異物>
散歩中に小石や枝が足に刺さって傷ができたり、夏場にはアスファルトの熱でやけどをしたりして炎症を起こすことがあります。
<ストレス・問題行動>
退屈や不安、環境の変化などのストレスが原因で、自分の足先を舐め続ける行動をとることがあります。
犬種別・環境別の注意点
指間炎は、犬種や生活環境によって発症リスクが異なります。以下のような点に注意しましょう。
<指間炎になりやすい犬種とその特徴>
シーズーやパグ、フレンチ・ブルドッグなどの短頭種は皮膚が敏感で、湿度やアレルゲンに影響を受けやすいため、指間炎を発症しやすい傾向があります。
また、トイ・プードルやマルチーズのように被毛が豊富な犬種では、足先や指の間の被毛が密になりやすく、その部分が蒸れて細菌が繁殖しやすくなるため注意が必要です。
<季節による発症のリスク>
梅雨や夏場など湿度の高い時期は、指の間が蒸れて菌が繁殖しやすくなります。雨上がりの散歩や水遊びの後には、足をしっかり乾かしましょう。
<散歩による発症のリスク>
屋外での散歩が多い犬は、アスファルトの熱や砂利によって小さな傷ができやすく、これが炎症の引き金になることもあります。散歩後は、足先に異常がないかチェックしてあげましょう。
<指間炎と他の疾患の関連性>
アトピー性皮膚炎や膿皮症などの他の皮膚疾患を抱えている犬は、指間炎を併発しやすい傾向にあります。慢性化させないためにも、定期的な皮膚チェックが重要です。皮膚以外の疾患でも関節痛や足先の知覚過敏による違和感で足先をなめることがあり、指間炎を発症することがあります。
愛犬が体をかゆがるときは要注意!犬のアトピー性皮膚炎についてより詳しく知りたい方はこちら
診断方法
指間炎の診断では、まず視診や問診を通して症状の傾向を把握します。
<視診・問診>
視診では皮膚の赤みや腫れ、分泌物の有無などを確認します。
問診では、症状が出始めた時期や生活環境について、飼い主様から詳しく伺い、総合的に状態を把握します。
また、指間炎は再発しやすい病気であるため、過去に同じような症状があった場合には、当時の治療内容や回復までにかかった期間なども確認し、今後の治療に役立てます。
<細胞診・培養検査>
症状が進行していたり、原因が特定しづらい場合には、皮膚の細胞を顕微鏡で確認したり、細菌や真菌の培養検査を行ったりします。これにより、適切な薬を選ぶことが可能になります。
<アレルギー検査>
再発を繰り返す場合や全身に皮膚症状がある場合には、アレルギー検査を行い原因となるアレルゲンを特定します。また除去食試験という方法で、食事アレルギーの確認をすることもあります。
治療方法
当院では、原因に応じて以下のような治療を行います。
・外傷がある場合:傷の洗浄と消毒を行います。
・感染症が見られる場合:抗菌薬や抗真菌薬を使用します。
・アレルギーの場合:除去食療法や内服薬などを用いて対応します。
■薬物療法
炎症や感染を抑えるために、軟膏やスプレータイプの外用薬を用いたり、内服薬を処方したりすることがあります。症状の状態によって薬を使い分けるため、自己判断で使用せず、必ず獣医師の指示に従ってください。
■足浴・シャンプー療法
薬用シャンプーや消毒液を使用して足を洗うことは、指間の皮膚を清潔に保ち、菌の繁殖を抑える効果があります。症状に合った製品を使うことが大切なため、使用方法や製品選びについては必ず獣医師に相談してください。
<治療期間と経過観察のポイント>
治療にかかる期間は、症状の重さによって異なりますが、数週間から1か月以上かかることもあります。症状が一時的に落ち着いても、自己判断で治療をやめず、獣医師の指示に従ってしっかりと経過を観察することが大切です。
ご家庭でできる指間炎のケアと予防法
日常生活の中でも、指間炎の予防や再発防止に役立つケアはいくつかあります。以下のポイントを意識して、愛犬の足元をしっかり守ってあげましょう。
<足のケア>
散歩のあとは、ぬるま湯や濡れタオルで足を丁寧に拭き、指の間までしっかり乾かしましょう。湿気が残ると、菌が繁殖しやすくなり、炎症の原因になります。
<被毛のケア>
指の間の毛が長いと蒸れやすく、汚れもたまりやすくなります。定期的なトリミングで足先の毛を短く保ち、清潔な状態を維持しましょう。
<ストレスケア>
犬がしきりに足を舐める行動は、ストレスが関係していることもあります。普段の生活の中で、安心して過ごせる環境を整えたり、リラックスできる時間をつくってあげたりすると良いでしょう。
また、また、舐めすぎによって症状が悪化するケースもあるため、エリザベスカラーや知育トイなどを使って舐める時間を減らすことも有効です。ただし、これらの対策が逆にストレスにならないよう、愛犬の様子を見ながら無理のない範囲で対応することが大切です。
<適切な栄養管理>
皮膚の健康を保つためには、栄養バランスの取れた食事が欠かせません。皮膚のバリア機能を補助するサプリメントの使用も一つの方法です。サプリメントの使用については、獣医師に相談しましょう。
まとめ
犬の指間炎は、かゆみや違和感によって大きなストレスとなることがあります。さらに、再発しやすい病気のため、早期発見・早期治療がとても重要です。もし、いつもと違う様子が見られた場合は、迷わず動物病院を受診しましょう。
再発を防ぐためには、日常のケアや生活環境の見直しも欠かせません。
当院では、症状の程度や犬の性格に合わせて、オーダーメイドの治療を行っております。少しでも気になる症状がありましたら、お気軽にご予約・ご相談ください。
■関連する記事はこちら
健康な今だからこそ受けたい!犬や猫の定期健診で見える未来とは?詳しくはこちらから
埼玉県川口市・さいたま市(浦和区)・越谷市を中心に診療を行う
森田動物医療センター
当院の診療案内はこちら
※お電話でもご予約・ご相談を承っております