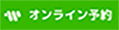2025/09/24
最近、愛犬が「散歩中に息が荒くなって苦しそう」「寝ているときのいびきが気になる」と感じたことはありませんか? 特にフレンチ・ブルドッグやパグ、ボストン・テリアなどの短頭種の犬では、こうした呼吸の異常が見られることが少なくありません。
こうした呼吸の乱れは、ただの「その犬種特有の個性」ではなく、「短頭種気道症候群(BOAS:Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome)」という進行性の疾患が関係している可能性があります。この病気を放置すると、日常生活に支障をきたすだけでなく、命に関わる深刻な状態に進行することもあるため、早期発見と適切な対応がとても重要です。
今回は犬の短頭種気道症候群について、特徴や症状、診断方法、治療方針、さらには日常のケア方法などを解説します。

■目次
1.短頭種気道症候群とは?
2.主な症状と重症化のサイン
3.診断方法と専門的評価
4.森田動物医療センターの治療方針
5.日常管理と再発予防
6.まとめ
短頭種気道症候群とは?
短頭種気道症候群とは、鼻から喉、気道にかけての構造的な問題が原因で、正常な呼吸が妨げられる疾患です。短頭種とはマズル(鼻先)が短く、顔が平たく見える犬種のことで、以下の犬種に多く見られます。
・フレンチ・ブルドッグ
・パグ
・シーズー
・ボストン・テリア など
この病気の特徴は、複数の解剖学的異常が組み合わさって発症する点にあります。具体的には、以下のような状態が複合的に関与します。
・外鼻孔狭窄:鼻の穴が狭く、呼吸時に空気をうまく吸い込めない状態
・軟口蓋過長症:喉の奥にある柔らかい部分(軟口蓋)が長すぎて気道を塞いでしまう状態
・喉頭虚脱:喉の軟骨構造が変形してしまい、気道が狭くなってしまう状態
・気管低形成:気管が生まれつき細く、空気の通り道が狭くなっている状態
これらの異常は成長に伴って悪化することが多く、加齢とともに症状が目立つようになるケースもあります。
主な症状と重症化のサイン
短頭種気道症候群では、軽度な症状から命に関わる重篤な状態まで、さまざまな段階の臨床症状が見られます。特に飼い主様が気づきやすい代表的な症状としては、以下のようなものがあります。
・散歩中や興奮時に「ガーガー」「ゼーゼー」といったいびきのような呼吸音がする
・暑い日や運動時にすぐに息が荒くなり、呼吸が苦しくなる
・食事中にむせたり、飲み込んだ直後に吐き戻したりすることがある
さらに病状が進行すると、次のような緊急性の高い症状が現れる場合があります。
・ストレスや少しの運動で急激な呼吸困難を起こし、意識を失って倒れてしまう(失神)
・舌や歯茎が紫色になる(チアノーゼ)など、酸素不足を示す兆候が見られる
このような症状は命に関わる可能性があるため、早急な受診が必要です。
診断方法と専門的評価
呼吸症状のある犬が短頭種である場合、ある程度の予測は可能ですが、正確な診断とリスク評価のためには、多角的な検査が不可欠です。当院では、以下の流れで診断を進めます。
①問診:飼い主様から日常生活での様子や症状の出方について詳しく伺います
②身体検査:呼吸音や鼻、口の中などの外見的異常を確認します
③レントゲン検査:気管や胸部の状態を画像で把握します
④内視鏡検査:全身麻酔下で喉や気道の奥を直接観察し、軟口蓋の長さや喉頭の変形などを詳細に評価します
これらの情報を総合的に判断し、どの程度の治療が必要か、また手術を行う場合はそのタイミングについても慎重に見極めていきます。
なお、当院では「他院で手術や治療を受けた犬の再評価(セカンドオピニオン)」にも対応しております。現在の治療方針に不安を感じている場合や、他の選択肢を知りたいというご希望がありましたら、お気軽にご相談ください。
森田動物医療センターの治療方針
短頭種気道症候群に対する治療には、「外科的治療(手術)」と「内科的治療(薬や生活管理)」の2つの方法があります。当院では「必ず手術を行うべき」とは考えておらず、犬の年齢、症状の重さ、全身状態などをしっかり評価した上で、飼い主様とご相談しながら治療方針を決定しています。
<外科的治療>
解剖学的な異常を根本から改善することを目的とします。状態に応じて、以下のような術式を選択します。
・外鼻孔拡張術:狭い鼻の穴を広げて空気の流れを改善する手術
・軟口蓋切除術:過長した軟口蓋を適切な長さに整え、気道の閉塞を解消する手術
これらの手術は、特に若いうちに行うことで予後が良くなる可能性がありますが、全身麻酔を伴うため、術前の全身評価やリスク説明を丁寧に行った上で、実施の有無を判断します。
<内科的治療>
手術が難しい場合や軽度の症状には、以下のような治療を組み合わせて行います。
・呼吸の補助となる内服薬(気管支拡張薬、消炎剤など)
・酸素吸入による一時的な呼吸サポート
・食事療法や運動制限による体重管理
肥満は呼吸器への負担を大きくするため、体重管理は非常に重要な内科的アプローチです。継続的な体重のコントロールにより、手術の必要性を下げられるケースもあります。
日常管理と再発予防
短頭種気道症候群では、日々の生活環境が症状の出方に大きく関係してきます。症状の緩和や再発の予防のためには、以下のようなご家庭での配慮が重要になります。
・エアコンなどを活用し、室内の温度や湿度を常に快適な状態に保つ
・夏場の外出は気温が低い早朝や夕方を選び、暑さによる呼吸の悪化を避ける
・激しい運動や興奮を避け、定期的に休憩時間を設けるようにする
・高カロリーの食事やおやつを控え、適切な運動を取り入れながら肥満を予防する
・手術後も定期健診を継続し、再発や症状の悪化を早期に発見できるようにする
このような日常管理の積み重ねによって、治療の効果を高め、再発のリスクを減らすことが可能になります。
まとめ
短頭種気道症候群は、フレンチ・ブルドッグやパグなどの犬種に特有の進行性疾患です。見た目の可愛らしさの裏に、深刻な呼吸の問題が隠れていることも少なくありません。呼吸困難や失神といった症状は命に関わる危険もあるため、気になる症状があれば決して様子見をせず、できるだけ早く動物病院に相談することをおすすめします。
当院では、それぞれの犬の状態に合わせて最適な治療法をご提案し、飼い主様と一緒に治療方針を決定しております。「手術が必要かどうか不安」「今の治療法が本当にベストなのか知りたい」と感じた際にも、どうぞお気軽にご相談ください。
当院では、犬のQOL(生活の質)を最優先に考え、呼吸の苦しさを少しでも和らげられるよう、飼い主様とともに最善のサポートを行ってまいります。
分からないことがありましたら、お気軽にご相談ください。
⬇️🌟この情報が役に立った方は、星をタップして応援してください🌟⬇️
埼玉県川口市・さいたま市(浦和区)・越谷市を中心に診療を行う
森田動物医療センター
当院の診療案内はこちら
※お電話でもご予約・ご相談を承っております
<参考文献>
Brachycephalic obstructive airway syndrome: much more than a surgical problem – PMC (nih.gov)