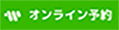2025/11/07
愛犬が「急に嘔吐した」「元気がない」といった様子を見て、不安を感じた飼い主様も多いのではないでしょうか。
これらの症状は一時的な体調不良のように見えることもありますが、実は「膵炎」を引き起こしている可能性があります。膵炎は犬に多く見られ、放置すると命に関わることがあるため、早期対応が何よりも大切です。
今回は犬の膵炎について、原因や症状、診断方法、治療方法、予防のポイントなどを解説します。

■目次
1.犬の膵炎とは?|急性と慢性の違い
2.症状
3.犬の膵炎の原因とリスク因子
4.診断方法
5.治療方法
6.予防と飼い主様にできること
7.まとめ
犬の膵炎とは?|急性と慢性の違い
膵炎とは、膵臓に炎症が起こり、本来は食べ物の消化を助ける酵素が自らの膵臓を傷つけてしまう病気です。犬では特に発症が多く、「急性膵炎」と「慢性膵炎」に分けられます。
<急性膵炎>
突然発症し、数時間から数日のうちに急速に悪化する場合もあり、放置すると命に関わる可能性もあります。そのため、症状が軽く見えても油断せず、早期に治療を開始することが重要です。
<慢性膵炎>
炎症が長く続き、症状を繰り返すタイプです。時間の経過とともに膵臓の働きが低下し、糖尿病などの合併症を引き起こすこともあります。
症状
膵炎の代表的な症状には、以下のようなものがあります。
・嘔吐や下痢
・食欲不振
・元気がない
・お腹を痛がる、触られるのを嫌がる
・背中を丸めてじっとしている姿勢
初期のうちは「少し食欲がないだけ」と見過ごされがちですが、特に急性膵炎の場合は数時間で症状が急速に悪化することもあります。そのため、軽視せず、早めに動物病院を受診することが大切です。
犬の膵炎の原因とリスク因子
膵炎はさまざまな要因で発症します。代表的な原因には以下のようなものがあります。
・脂肪分の多い食事や、人間の食べ物を誤って食べてしまう
・肥満や高脂血症(血液中の脂肪が多い状態)の傾向がある
・ミニチュア・シュナウザーなどの特定犬種での発症リスク
特に高脂血症は膵炎との関連が深く、脂質の代謝異常が引き金になることがあります。膵炎は「生活習慣病」ともいえる側面があり、日常の食事管理や体重コントロールが予防のカギとなります。
診断方法
膵炎は、見た目の症状だけでは正確に判断することが難しい病気です。そのため、複数の検査を組み合わせて総合的に診断します。代表的な検査は以下の通りです。
<血液検査>
血液中の炎症反応や脱水の有無を確認するとともに、膵炎に特異的なマーカーである「犬膵特異的リパーゼ(Spec cPL)」の値を測定します。この数値が高い場合、膵炎の可能性が高いと判断されます。また、肝臓や腎臓など他の臓器の状態も同時にチェックし、合併症の有無を把握します。
<レントゲン検査>
腹部全体の構造を確認する検査です。膵臓そのものははっきりと映らないこともありますが、膵炎によって腸がガスで膨らんでいたり、腹腔内に異常がないかを確認したりするうえで有効です。
<エコー(超音波)検査>
膵臓の形や腫れ、周囲の炎症の程度をより詳しく観察できる検査です。エコーでは膵臓の腫大や、周囲の脂肪組織の変化、腹水の有無などをリアルタイムで確認できます。痛みや麻酔の必要がなく、体への負担が少ない検査として広く行われています。
▼当院の心電図、血圧、レントゲン、エコー検査についてより詳しく知りたい方はこちら
▼当院の血液検査、尿検査、糞便検査についてより詳しく知りたい方はこちら
また、必要に応じて、尿検査や便検査、追加の画像検査(CTなど)を行う場合もあります。これらの検査を総合的に評価することで、膵炎の有無だけでなく、重症度や合併症の有無を正確に判断します。
当院では、眼科や歯科などの専門分野に対応しながら、内科・外科を含めた総合診療体制を整えており、膵炎のように全身管理が必要な疾患にも適切に対応しています。
何かわからないことがありましたら、お気軽にご相談ください。
治療方法
治療方法は「急性膵炎」と「慢性膵炎」で異なります。
<急性膵炎の場合>
脱水を防ぐための点滴や、炎症を抑える薬の投与を中心に行います。当院では、発症からできるだけ早い段階で治療を開始することで、薬の効果を高め、回復の可能性を最大限に引き出すことを重視しています。
<慢性膵炎の場合>
長期的な管理が必要になります。主な治療は食事療法で、膵臓への負担を減らすために低脂肪フードを用います。さらに、体質や症状に合わせた治療を組み合わせ、再発防止と継続的なフォローアップを行うことが重要です。
予防と飼い主様にできること
膵炎の予防には、飼い主様の日常のケアが欠かせません。特に、以下のような点を意識しましょう
・チーズや揚げ物など、脂質の高い食べ物を与えない
・適正体重を保ち、肥満や高脂血症を防ぐ
・定期的に健康診断を受け、血液検査で早期の異常を確認する
・「少し様子が変だな」と感じたら、早めに動物病院へ相談する
このように、日々のちょっとした管理が膵炎の発症リスクを大きく減らすことにつながります。
▼犬と猫の健康診断の重要性についてより詳しく知りたい方はこちら
まとめ
犬の膵炎は、放置すると命に関わる危険な病気ですが、早期に治療を行えば回復できる可能性が十分にあります。
当院では、急性膵炎の緊急対応から慢性膵炎の長期管理まで、一貫した治療体制でサポートしています。また、眼科や歯科などの専門診療に加え、内科・外科・生活習慣管理を含めた総合的なトータルケアを行っております。
愛犬の体調に少しでも不安を感じたときは、どうぞお気軽にご相談ください。飼い主様とともに、愛犬の健康を守るお手伝いをいたします。
⬇️🌟この情報が役に立った方は、星をタップして応援してください🌟⬇️
埼玉県川口市・さいたま市(浦和区)・越谷市を中心に診療を行う
森田動物医療センター
当院の診療案内はこちら
※お電話でもご予約・ご相談を承っております